
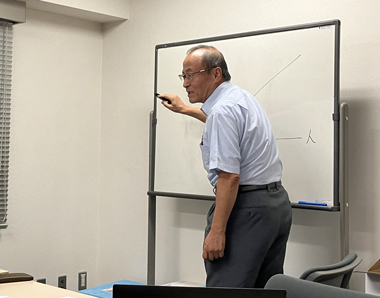
インドネシア奨学生への講義の様子
2024年初め、ABICから三井物産インドネシア奨学基金の留学生向けにインドネシアの社会課題に関する講義を行う講師を公募しているというお知らせメールがあった。三井物産は1992年に同基金を設立し、インドネシアから毎年2人の留学生を日本に招致し、日本語教育を行った上で、大学入学試験合格後の授業料、生活費を卒業まで全面的に支援している。インドネシア全国の高校生が数千人単位で応募してくるので、わずか2人の枠に合格するのは至難である。その優秀な学生たちに、大学卒業時までにインドネシアの社会課題に関して考え、行動し、卒業時に発表してもらおうという新たな試みを、現在の大学2年生から行うことになった。これは、社会課題に向き合い、自らの経験や学問を生かして世界で活躍できる人材を育成することを目指したプログラムである。新しいサービスや事業を開拓し、日々変わっていく世界のニーズに対応していくというのも商社の重要な活動だが、社会貢献の一環として、直接若人の学業やその志を支援していく活動もあっていい。大学の学業にあまり支障がない範囲で、カリキュラムとは離れて、自国の社会課題に直接向き合い考えていく時間を持っていいし、それに関係する講師の講義・助言を聞くのも意味がある。
私は三井物産のプロジェクト本部に所属していたが、30歳代後半から40歳代にかけて11年、また同社に所属しながら50歳代にジェトロ(日本貿易振興機構)の経済連携アドバイザーとして1年半、通算12年半ジャカルタに駐在した。知りたいことは多く、教えることも好きで、若人も大好きなので、現在大手学習塾の講師を務めているが、年数回程度であれば、インドネシアの学生たちに日本語で講義することもできるだろうと考えた。ABICへの応募資料には、中国経済に関してまとめた書籍の抜粋も付け、経済動向分析も行ってきたことも示した。
幸いに講師として採用ということになり、インドネシアの社会課題について何を話すか考え始めた。いくつかのテーマ候補を挙げた中から、6月の第1回の講義は「社会格差」を取り上げることを、関係先と相談の上決めた。インドネシアに限ることではないので、同国を強く意識しながら、米国、中国、日本および世界全体に広がる経済格差、貧富格差、教育格差、男女格差について俯瞰していった。社会全体の活気を保ちながら自由に活動しつつ、ある程度の平等を実現しなくてはならない。ジニ係数・累進課税、日本の過去30年にわたる非正規雇用労働者の増加とこれに伴う労働市場の課題、大学進学率と最先端技術(ノーベル賞)、内閣閣僚あるいは国会議員における男女比率など多岐にわたる分野で、データを示しつつ講義を行った。約十人の学生たちも熱心に聞いてくれた。
10月の第2回の講義は「人工知能(AI)」を取り上げた。AIの発展過程をレビューし、人間の知的活動分野を部分的に凌駕してきた歴史を振り返った。そして、特にインドネシアや日本における医療・教育分野でのAI活用事例を紹介し、今後どのようにAIと共に歩むのかを、社会課題の一つとして考察した。
じきに3回目の講義を行う予定だが、全力を尽くし、学生たちと共に学びたい。新しく始まったこの社会課題プロジェクトは、学生の自主的な学びと、主体的なアクションを期待しており、本活動を通じて、インドネシアのリーダーたちが育つ一助となることを祈っている。